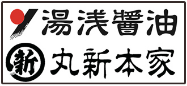金山寺味噌とは

● 金山寺味噌とは?
金山寺味噌とは和歌山県発祥の「なめ味噌」
金山寺味噌(金山寺みそ)とは、和歌山県発祥のなめみそ(なめ味噌)、おかず味噌です。
味噌汁に使う普通味噌と違い、金山寺味噌は、米・大麦・大豆の穀物に麹菌をつけて、なす・瓜・生姜・しそなどの野菜と一緒に自然発酵させているので野菜の旨みが引き出され、甘みと塩味、深みのある香りの良い発酵味噌です。
ピーナッツ味噌や肉味噌、ゆず味噌などのように火入れして仕上げる加工味噌とは違うなめ味噌になります。
中国から紀州の興国寺 (和歌山県由良町)に伝わった径山寺味噌(徑山寺味噌、きんざんじみそ)が由来となったもので、和歌山県の特産品で、和歌山県推薦優良土産品に指定されています。
もっと詳しい作り方は、こちらのページをご覧ください。
https://www.marushinhonke.com/f/kinzanji-kodawari
● 金山寺味噌の歴史とは?
実は長い金山寺味噌の歴史とは?
金山寺味噌は、その名からも想像できるように、金山寺(正しくは鎮江府金山竜遊江寺)という中国の宋の時代のお寺から覚心(法燈国師)という名の僧によって、和歌山県の由良にある臨済宗 鷲峰山興国寺に伝えられました。
鎌倉時代、お寺に人を集める目的で作り方を地元の人に教え、栄養食、健康食として盛んに作られました。たまたま湯浅の水が味噌を作るのに適していたことと、熊野古道の宿場町であったことから、すぐにその製法が湯浅に広まりました。
金山寺味噌を作る段階で野菜から出る余分な水分がカビの腐る原因になるとして、それまで捨てられていましたが、この汁「溜まり(たまり)」(醤油の元祖)を調味料として使ってみると以外にも美味しかったので、始めから、醤油を作るつもりで味噌を仕込むことが湯浅で行われるようになり、改良を重ねて今の醤油になりました。
やがて湯浅には全国から醤油の作り方を習いに来て、その製法を持ち帰り、全国に広まったと言われていますので、金山寺味噌が「湯浅醤油の元祖」、「日本の醤油の元祖」と言われています。
金山寺味噌の歴史:詳しくはこちら
● 金山寺味噌のレシピ・食べ方とは?
金山寺味噌の人気の食べ方とは?
金山寺味噌の特徴は、野菜の旨みが引き出され、甘みと塩味、深みのある香りの良い味噌です。
食べ方、使い方としては、ご飯のお供やお粥、お茶漬け、酒の肴、もろきゅうにおすすめです。
他の食べ方としては、冷奴にのせたり、チーズのトッピング、焼き魚、鶏肉や豚肉などを焼いてトッピングしたり、野菜や肉を炒める時など調味料として一緒に炒めても美味しいレシピになります。
● もろみ味噌と金山寺味噌の違いとは?
もろみ味噌と金山寺味噌の食べ方の「大きな」違いとは?
金山寺味噌(金山寺みそ)は、もろみ味噌に似ていますが、やはり色々な野菜が入っているので、旨味があり、具を選ぶ楽しみや食感を楽しめるおかず味噌で、紀州では茶粥のお供に昔から食べられている伝統食です。
金山寺味噌(金山寺みそ)と、もろみ味噌は、日本の伝統的な発酵食品として長い歴史を持っています。しかし、これらの味噌はその成分、風味、そして用途においていくつかの違いを持っています。
【 原材料:金山寺味噌ともろみ味噌の違いとは? 】
金山寺味噌ともろみ味噌「食感と風味」はどう違う?
金山寺味噌は、米・大麦・大豆の穀物に麹菌を使って発酵させたもので、さらになす、瓜、生姜、しそなどの様々な野菜と一緒に発酵させています。これにより、野菜の風味と旨みが加わります。
もろみ味噌は、一般的には大麦や米を基にした味噌で、魚や海草、野菜を加えることは少ないです。
食感と風味:
金山寺味噌は、野菜の具が多いため食感が楽しめ、もろきゅうとして楽しんだり、酒の肴としてなめる(その理由で「なめ味噌」とも呼ばれます)楽しめたり、多様な風味が特徴的です。
【 使い方:金山寺味噌ともろみ味噌の使い方の違いとは何でしょうか? 】
金山寺味噌:「なめ味噌」ならではの楽しみ方
金山寺味噌は、おかず味噌として、茶粥のお供や、肉や魚の料理のトッピングとして人気です。
もろみ味噌は、一般的にもろきゅうや肉や魚のトッピングに使用されることが多いです。
醤油を搾った後のひしおもろみなどは、調味料として炒め物や煮物、漬物に使用されることが多いです。
【 地域性:金山寺味噌の地域性とは? 】
金山寺味噌は和歌山伝統のなめ味噌(おかず味噌)
金山寺味噌は特に和歌山県で有名で、紀州地方の伝統食として受け継がれてきました。
もろみ味噌は、特定の地域に強く結びついているわけではありませんが、全国的に広く知られています。
● 金山寺味噌の特徴とは?(まとめ)
金山寺味噌:もろみ味噌に似ているが和歌山に根ざした特徴
総合的に言えば、金山寺味噌は、もろみ味噌に似ているものの、その風味や用途、そして背景にある歴史や文化において、和歌山に根ざした独自の特徴を持っています。
<金山寺味噌の食べ方>
1881年から金山寺味噌を作り続けている湯浅醤油、丸新本家がおすすめする金山寺味噌の食べ方、レシピをお伝えいたします。
 |
1) ご飯のお供に野菜の旨味とほどよい塩気がたまらない金山寺味噌。 |
 |
2)お粥に乗せるご飯のお供と同じくらいおすすめするのが、お粥に乗せる。 |
 |
3)お酒の肴におすすめ「なめ味噌」そして何といっても、なめ味噌でもある金山寺味噌はお酒の肴に最適! |
 |
4)もろきゅう(金山寺味噌で)もろきゅうといえば、お酒好きには最強のおつまみ、という方も多いはず。 |
 |
5)チーズ意外とチーズとの相性もよい金山寺味噌。 |
1) ご飯のお供に |
 |
野菜の旨味とほどよい塩気がたまらない金山寺味噌。
|
2)お粥に乗せる |
 |
ご飯のお供と同じくらいおすすめするのが、お粥に乗せる。
|
3)お酒の肴におすすめ |
 |
そして何といっても、お酒の肴におすすめです! 和歌山県で最強とも言えるお酒のつまみ、金山寺味噌。
|
4)もろきゅう |
 |
もろきゅうといえば、お酒好きには最強のおつまみ、という方も多いはず。
|
5)チーズ |
 |
意外とチーズとの相性もよい金山寺味噌。
|
 |
紀州金山寺味噌が和歌山県で初めてGI(地理的表示)認定を受けました |
2017年8月、「紀州金山寺味噌」が地理的表示(GI:Geographical Indication)保護制度に和歌山県の産品として初めて登録されました(全国では39番目の登録。「味噌」の登録は全国初)。登録生産者団体は紀州味噌工業協同組合。
GIマークは、世界的には、シャンパンやパルマハム、神戸ビーフや八丁味噌など、地域で長年育まれた伝統と特性を有し、その品質等の特性が生産地と結びついている農林水産物や食品の名称を、知的財産として保護するものです。
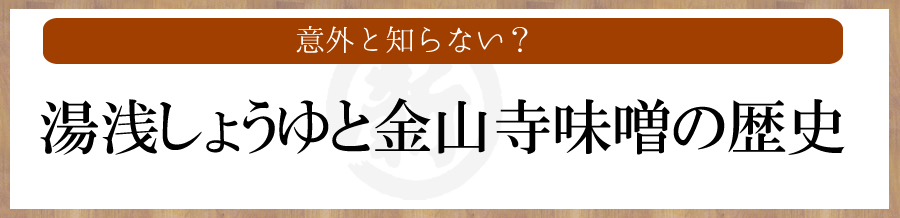
● おかず味噌と金山寺味噌。日本の醤油の起源とは?
おかず味噌(なめ味噌)である金山寺味噌の歴史とは?
おかず味噌(おかずみそ)と呼ばれる金山寺味噌(金山寺みそ)と日本の醤油の起源について、その歴史的背景と現在をお伝えします。
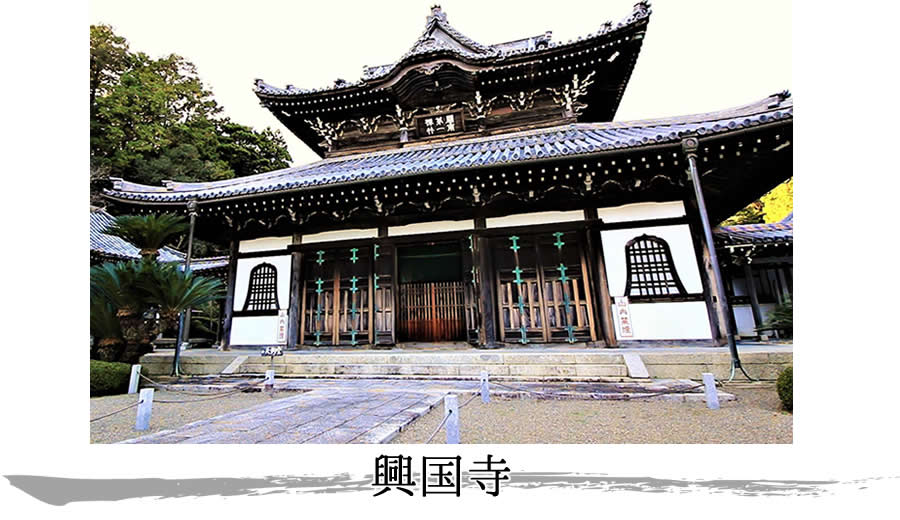
金山寺味噌とはその名からも想像できるように、金山寺(正しくは鎮江府金山竜遊江寺)という中国の宋の時代のお寺から覚心(法燈国師)という名の僧によって、和歌山県の由良にある臨済宗 鷲峰山興国寺に伝えられました。
この覚心和尚とはどんな人?
覚心の生まれは、今の長野県松本市の豪族と呼ばれる力のある家の子として誕生しました。
また彼は、座禅を組んで悟りをひらく禅宗で名高い臨済宗の高僧でもありました。
彼は、15歳で天台宗の厳殿寺に修学し、19歳であの有名な東大寺に学び、 そして真言密教を三輪寺で学んだ後に高野山に登りました。 高野山に登った覚心が、なぜ和歌山県由良の興国寺なのか。
それには悲しくも情に溢れた歴史が隠されています。

鎌倉時代、三代将軍・源実朝が、甥・公暁に鶴岡八幡宮で殺されました。

その時、実朝の忠臣・葛山五郎は、君主のかねてよりの夢であった宋へ渡る船の準備を由良の港で行っていました。
主人の死を知り葛山は、その苦堤をとむらうため高野山に入ります。その時に知り合ったのが若い覚心でした。
故主人・実朝の供養の様子を聞いた当時の尼将軍・北条政子は、葛山にその供養料として由良の地を与え、一寺を建てたのです。
これが興国寺の始まりです。
しかし、葛山は次第に主人・実朝がずっと憧れ続けていた宋の国に実朝の遺骨の半分を納めたいと思うようになります。年老いた葛山の宿願を果たしてくれたのが、覚心でした。
覚心が宋に渡り、中国5大禅寺のひとつである径山寺(興聖万寿禅寺)に赴き、
他の寺でも中国で通算約5年修行し、その間に実朝の遺骨を広利禅寺に納め、
金山寺味噌の製法と四人の宋の人をつれて由良の興国寺に帰ってきました。
その後、覚心は、葛山からその才を見込まれて興国寺の住職となり、
後に、亀山上皇、後醍醐天皇より法燈禅師、法燈円明国師と贈り名されました。
● 湯浅が金山寺味噌の発祥地となった理由とは?
金山寺味噌と醤油発祥の地「湯浅」の関係とは?
金山寺味噌のたまりが醤油の元祖といわれているので、本来なら、由良が醤油発祥の地となるはずがなぜ、少し離れた山漁村の湯浅が醤油発祥の地といわれているのでしょうか。
まずは、由良と湯浅との地理的な距離をご説明します。
由良町は、和歌山県の日高という所にある港町で、ちょうど和歌山市と白浜との中間点位で、平地が少なく、山ぶかい所です。
一方、湯浅町は、主に漁村として栄えていた町で、由良の北にある隣町になります。
湯浅町は、熊野三山へと続く熊野古道の宿場町として栄え、熊野古道が唯一商店街を通る町でもあり、船での運搬も盛んに行われていました。
交通上重要な位置にあった湯浅だからこそ、醤油の町として発展し、近世に入り次第に商業都市として発展しました。
そして、白壁の土蔵、格子戸や虫籠窓など、醤油醸造の伝統を感じる家並みが残る東西約400m、
南北約280mの一帯は平成18年に文部科学省から、「重要伝統 的建造物群保存地区」に選定されました。
醤油醸造など商工業を中心に発展した町が今も地割を残し、近世から近代にかけての重厚な町並みが歴史的風致をよく 残す貴重なものと認められ、街歩きの観光スポットとなっています。


鎌倉時代、興国寺では、野菜と大豆から作られる金山寺味噌を栄養食、健康食として盛んに作られましたが、
たまたま湯浅の水が味噌を作るのに適していたため、すぐにその製法が湯浅に広まったのです。
金山寺味噌を作る段階で野菜から出る余分な水分が、カビの腐る原因になるとしてそれまで捨てられていました。
ところが、この汁を調味料として使ってみると以外にも美味しかったので、
始めから、醤油を作るつもりで味噌を仕込むことが湯浅で行われるようになり、改良を重ねて今の醤油になりました。

湯浅から、醤油が商品として出荷されたのは、今から約400年前の安土・桃山時代の文献に記されているそうです。
その後、徳川御三家紀州藩の保護のもと藩の専売制も手伝って、
文化・文政の時には1000戸の湯浅町に約92件もの醤油屋があったとされています。
享保の改革で有名な享保年間には、湯浅の人々が今の房総半島に渡り、銚子に出かけ、醤油の生産を始めています。
そのなごりとして、その半島の地名には和歌山の地名と同じ所があります。
また、全国から醤油づくりを習いにやって来て、各地で醤油づくりが広がっていったことも文献に残っています。
現在、湯浅町には造り醤油のお店は数軒残されているだけですが、湯浅の名を全国に知らしめ、
伝統産業である醤油造りや金山寺味噌造りは、今の本物を求める時代のニーズに応えられる物と言えるのではないでしょうか。

丸新本家は、この醤油の元祖といわれる金山寺味噌のたまりを再現した唯一の蔵元です。
野菜の旨みや栄養が凝縮した『金山寺たまり 九曜むらさき』は、塩分を13%にまでひかえ、塩辛くなくさらっとしたたまり醤油です。
2006年から毎年連続モンドセレクションにおいて、10年間最高金賞を受賞し、高品質商品として世界でも認められました。
お刺身以外にも、漬物や冷奴等かけ醤油としてお使いください。和風ステーキなどのお肉料理なんかにも合うと評判です。
金山寺味噌の魅力とはどんなものなのか?
一度味わっていただくと実感いただけると思います。
是非、ご賞味ください。。

|
1881年から受け継いだ金山寺味噌。 |
社長ブログに詳しい記載があります。
こちらもご覧下さい。
https://ameblo.jp/yuasasyouyu/entry-12396789318.html